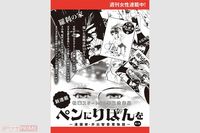「当時はベストセラーといっても何十万部も売れたわけではないので、どうやって売っていくか、どう利益を得るか、今より大変だった気がします」
と、木内さん。
この時代は、木の板に文字や絵を彫り、絵の具をのせ、紙を当てて1枚ずつ刷り、本や浮世絵を作っていた。手間もかかる、シビアなビジネスだった。それでも、初代蔦重なら「よっしゃ、やりましょう」と言ってくれたのではないか。木内さんは、笑いながら語ってくれた。
「そうかもしれませんね。蔦重も二代目になっていたので、決断力が弱くなったりしている感じはありますね」
リズム感のある文章はスポーツが関係?
二代目蔦重たち版元の慇懃な物言い、鈴木牧之の新潟弁、山東京伝の軽快な江戸弁、曲亭馬琴の屈折したセリフなど、言葉遣いにもそれぞれのキャラクターが立っていて、すぐそこにいるように感じられるのも本書の魅力だ。
「当時の暮らしや史実をよく調べて、資料も読み込んで、“ヨシ、大丈夫だ!”となったところで書き始めます。登場人物が自分の知り合いみたいに思えて“あのとき、ああだったよね”みたいに、自分で聞いたんだっけ?と思えるくらいになったら書きます。年表にすると、遠くなるというか、知り合いではなくなってしまうんですよね」
おっとりした雰囲気の木内さんだが、高校生までスポーツ少女だった。
「中学は卓球部、高校ではソフトボール部。強豪校でスポーツざんまいでした。高校のときは、膝を柔らかくする目的で新潟のスキー場に年に何回も行きました。友達もみんな体育会系のせいか、一日中黙々と、コースを何本も滑っていましたね(笑)」
読み手をグイグイ引っ張っていくリズム感のある文章は、運動神経のいい身体だから生まれたのかもしれない。
1816年、山東京伝は56歳で死去。このとき牧之は47歳。雪国の話を書き始めて20年の歳月が流れていた。
原稿は曲亭馬琴の手に渡り、牧之の元には「京伝亡き後、出版を請け負う」との手紙が届く。ところが『南総里見八犬伝』などの執筆に忙しいからと先延ばしにされ、音沙汰なしで10年以上が過ぎる。
「馬琴は、いいものを仕上げるために執拗にやる人で、すごくクセが強い。必ずしも性格が悪いわけではないと思うんですが、牧之から見ると何なんだよってなりますね」