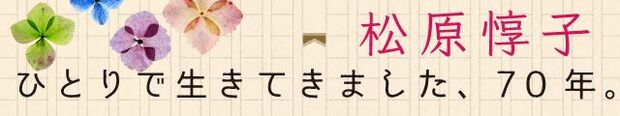1986年『女が家を買うとき』(文藝春秋)での作家デビューから、71歳に至る現在まで、一貫して「ひとりの生き方」を書き続けてきた松原惇子さんが、これから来る“老後ひとりぼっち時代”の生き方を問う不定期連載です。

第11回
石飛幸三先生のお話を聞いて感動したこと
「死ぬのは気持ちがいいらしい」
人生100年時代と言われるようになって久しいが、100年以上、生きたいと本気で思っている人がどれだけいるだろうか。友人の母親も今年で100歳を迎えるが、見た目は元気そうだが、頭も身体も年相応に弱ってきていて、見ているのが辛いと娘は語る。
著書『長生き地獄』(SBクリエイティブ)でも書かせていただいたが、死を考えるとき、苦しまずにスーと逝けますようにと、願うしかない。
昨年、「平穏死」を提唱されている石飛幸三先生のお話を聞く機会を得た。先生のご著書は何冊も読ませていただいているが、本で知るのと、実際に本人から聞くのでは、心への響き方が天と地ほど違う。改めて、足を運ぶことの大事さを痛感した。皆さんも、本を読んで共感したら、是非、著者の講演会に行って生で見てきてください。
石飛先生は御年83歳、世田谷区の特別養護老人ホーム「芦花ホーム」の常勤医をされている。慶応大学医学部出身の血管外科医だった先生がメスを捨て、人間の終末期と寄り添おうと決意したのは、世界で初めてホスピスを作ったシシリー・ソンダース氏を訪問したことによる。
当時の日本では、ベッドに拘束され苦しみながら死にゆく末期がんの患者さんが、ここではのんびりと葉巻をくゆらせていたからだ。日本の医療の在り方に疑問を持ったということだ。
老人が口から食べられなくなるのは、ごく自然なこと
石飛先生は、約13年、芦花ホームの常勤医をなさっているが、死にゆく老人に医療行為をほとんどせずに、自然に看取っている。老人は、飲み込む機能の低下で誤嚥性肺炎になりやすい。日本の施設では、誤嚥性肺炎を起こすと胃ろうをさせるのが普通だ。口から食べられなければ胃に穴を開けて栄養補給すればいいという考え方からだ。また、胃ろうにすると介護するほうも、食べさせる手間がなくなり楽だからだ。
石飛先生は言う。「老人が、口から食べられなくなるのは、ごく自然なこと。死に向かっているからです」。それなのに、無理やり栄養を与えるのは拷問のようなものだと怒る。
わたしも取材で、胃ろうのまま何年も生かされている老人を見てきているので、よく理解できる。ムンクの叫びのような苦しい顔。声のない叫び。「胃ろうにすると、まだまだ生きますよ」の医師の言葉をうのみにして、了解してしまう家族があまりにも多すぎる。