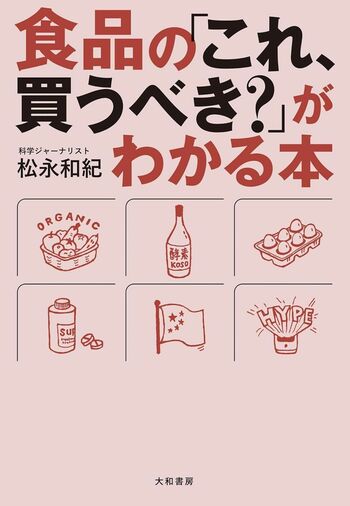豆腐や納豆には原材料に遺伝子組み換えについての表示義務があるものの、油や液糖、しょうゆなどでは表示義務がない。知らない間に口にしていることは往々にしてありそうだが、過剰な心配はいらない、と松永さん。
「市場に出回って30年がたちますが、全世界で健康被害は1件も報告されていません。日本では食品安全委員会がリスク評価をしてアレルギーなども検討し、問題ないと認められた食品しか流通していません。『老化を促進したり、食物アレルギーの増加を引き起こす』という説もあるようですが、これも根拠はゼロ」
ほかにも多くの食品が過去に流布されたイメージだけでジャッジされていることも多い。どんなものにもいい面と悪い面、注意すべき点と気にするほどでもない点がある。一部分だけのイメージで判断せず、生活スタイルや価格、味など総合的に見て、どれが自分に合っているかで食品を選ぶ、というのが正解だと松永さんは言う。
「甘味料を含む清涼飲料水をよく飲む人は、それに合う脂質や塩分過多の食事を好む傾向が。食品ではなく、栄養バランスが悪い食習慣が問題の本質だと思うのです」
食品に過敏になるより“食習慣”に注意
「日本人は料理を手作りすることへのこだわりが強く、それが加工食品や添加物の悪いイメージが払拭されない一因と考えています。安全で効率的に生活するためにも、適度に活用してもいいのでは」
松永さんが長年の取材から感じるのは、食品の安全性が脅かされるのは事業者側よりも消費者の段階が実は多い、ということ。
「例えば、賞味期限は開封前までが有効で、開封したら無効です。しかし、開封したあとも『この日付まで食べられる』と勘違いしている人は意外に多い。保存方法も表示どおりに守られておらず、結果、アレルギーや食中毒になることもあります」
食の健康情報にはつい飛びつきがちだが、出典元を必ず確認しよう。
「エビデンスの信頼性にもバラつきが。国など公の信頼できる研究機関からであれば信頼度は高いと考えます。新しい研究で覆されることもあるので情報更新も必須です」

教えてくれたのは……松永和紀さん●京都大学大学院農学研究科修士課程修了。毎日新聞の記者を経て独立。食品の安全性や環境への影響などを専門分野として執筆活動をする。著書に『食品の「これ、買うべき?」がわかる本』(大和書房)他。
取材・文/遊佐信子